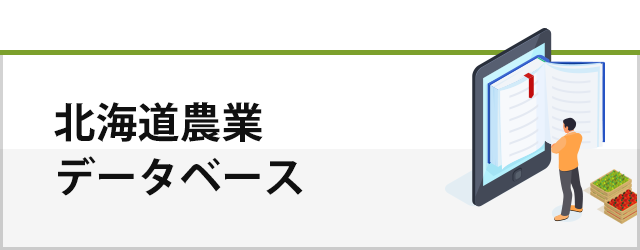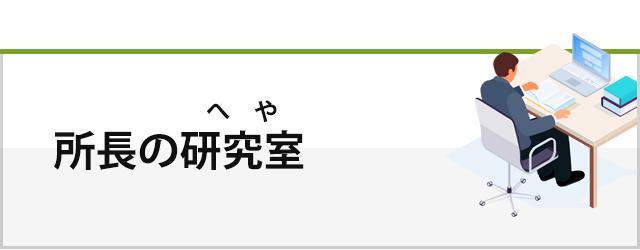北海道農業の振興に係わる諸問題について研究する実践的研究機関、北海道地域農業研究所公式Webサイト

受託研究
令和3年度(2021年度)
(1) 特定技能に関する調査研究 (委託者:北農5連)
概要
今日、様々な業種において労働力確保対策が大きな課題となっている状況で、技能実習制度に加え、2019(平成31)年4月に「出入国管理及び難民認定法」が改正され、新たな外国人材受け入れのための在留資格(特定技能)が創設された。その後、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、想定した雇用の確保が困難な状況も生まれている。改正法では、制度の在り方について施行後2年を経過後、関係者の意見を踏まえて検討するとしている。
そこで本研究では、農業分野における特定技能外国人材について、道内での就労実態、雇用者のニーズ等を踏まえ、その制度上の課題と要望を整理するとともに、現在実施中の特定技能実証試験を検証の上、JAグループ北海道としての特定技能制度を活用した今後の事業展開の実践的な方策を提起することを目指した。
とりまとめにあたっては、まず北海道における労働力需要の変化と外国人材の受け入れ状況を確認したうえで、2年来のコロナ禍による外国人雇用の変化を分析した。そこから導かれた特定技能外国人の雇用の本格化を指摘し、具体的な事例としてJA幌延町と浜中町酪農ヘルパー組合の調査・分析を行った。以上を踏まえ、JAグループ北海道の今後の方策に資するポイントを析出した。
第1に、今後、営農支援人材の派遣という枠組みの中で特定技能制度の活用を図る場合、人材の募集や選考段階で、日本語能力や実習経験以外の基準が必要となっていくということである。その際には、自動車免許や作業免許の取得も必須となる。現場では、未だ技能実習生も含む外国人材には免許取得は不可という認識が強いが、実際にはそうではない。さらに事故での保険適用などに不安を感じている者も多いが、労基法や労災適用が必須となっている現状においては、外国人材の在留資格に関わらず、問題はクリアされるはずである。むしろ、外国人材を日本人と同様に「労働者」として扱うかどうかは、受入側の問題であるということができる。加えて、このような認識の下では、リスク回避の十全な体制整備のために、共済事業面でのコンサルティングも含めた支援の余地もJAグループとして検討すべき課題であると思われる。
第2に、外国人・日本人に関わらず、専門人材としての待遇・労働条件面の改善である。JAグループ北海道としては、今後もより強くこれらに関連する事業の継続と改善を要請する必要がある。それが営農支援事業の担い手不足を解消し、ひいては外国人材の雇用条件の改善にも繋がっていくはずである。
第3に、利用料金設定の上方修正の必要性という点である。人材確保や人材の離職率の低下のための処遇改善は、利用料金の改善から検討を始めなければならないことを全道的にも周知していく必要がある。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 特定技能に関する調査研究報告書/令和3年度 北農5連委託研究事業
- 管理番号
- 706-475
- 委託者
- 北農5連
- 執筆者
- 宮入 隆、東山 寛
- 発行
- 2022.02
- キーワード
- 全国、北海道、宗谷管内、釧路管内、幌延、浜中、酪農
- 備考
- PDF公開あり(会員限定)
(2) 農地所有適格法人の事業承継支援に関する調査研究 (委託者:北農5連)
概要
2020年農林業センサスによると、全国の農業経営体数は107万6千であり、2015年より30万2千(21.9%)減少した一方で、法人経営体数は3万1千と、この5年で4千(13.0%)増加している。北海道についても、経営体数は約6千(14.0%)減少の3万5千に対し、法人経営体は479(13.0%)増の約4千となり、組織形態別での法人経営体の割合も、9%から12%に増加している。法人経営は生産基盤の維持のためさらに重要性を増すと思われる。
一方で、法人設立から一定期間が経過した経営体は、後継者確保や事業承継への対応が必要な時期を迎えているが、円滑な承継に向けた支援策が求められている。そこで本研究では、農地所有適格法人の事業承継について、優良事例の調査、課題の整理、効果的な事業承継の手法を検討し、JAグループ北海道の事業承継支援事業展開への実践的な方策を提起することを目指した。
調査は、道内の水田地帯、畑作地帯、酪農地帯に加えて、農業分野に明るい税理士事務所や法人支援に積極的に取り組むJAを対象に実施した。提言は以下の通りである。
1点目は、講師の派遣や費用の助成など、法人会が企画する事業承継の研修会のサポートである。事例地域のように、管内に農業法人が複数設立されている地域では農協が「法人会」を組織し、法人が抱えている悩みに応えるような研修(視察含む)を実施している。
2点目は、研修会の企画や費用の助成など、地元のJAとの連携のもとに法人従業員を対象としたスキルアップの研修機会のサポートを行うことである。事例でみたように、農業法人が外部人材に期待するところは大きい。最初は従業員としての雇用から始まるが、従業員から構成員へ、そして法人経営の中核を担う役員へ、というステップアップがある。
3点目は、法人に事業承継の方針や計画を作成するよう促すような取り組みの企画である。一例として考えられるのは、専門家(税理士)を法人に派遣して、株式の評価をしてもらうことである。事例で見たように、農業法人の事業承継は「早目の対応」「計画的な対応」が求められる。しかし、その必要性を理解していない法人経営者も少なからずいると思われる。
4点目は、事業承継の前段階からJAが法人に関わるという点である。農協が設立支援をした法人でも設立後は農協との関わりが薄くなり、税理士のみならず民間金融機関やコンサルタントが法人とコンタクトをとっている実態が明らかになった。事業承継は法人に深く関わるための切り口ではあるが、その前段で農協はもっと法人に関わる意義は少なくない。
5点目は、JAと法人の結びつきを強めるうえで、JAグループとして法人への「出資」を検討する点である。農業法人(農地所有適格法人)をめぐる情勢は、農外企業の出資制限を緩和する方向にある。アプローチの際には、「地域を守る法人(複数戸法人)」を優先するなど、メリハリをつけた対応がのぞましい。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 令和3年度 農地所有適格法人の事業承継支援に関する調査研究/令和3年度北農5連委託調査事業
- 管理番号
- 710-479
- 委託者
- 北農5連
- 執筆者
- 東山 寛、仁平 恒夫、小池 晴伴、小林 国之、井上 誠司、正木 卓、糸山 健介
- 発行
- 2022.03
- キーワード
- 北海道、渡島管内、檜山管内、空知管内、十勝管内、オホーツク管内、全般
- 備考
- PDF公開あり(会員限定)
(3) 連合会一体的・横断的事業展開に関する調査研究 (委託者:北農5連)
概要
JAグループ北海道(北農5連JA営農サポート協議会)では、多様化する経営体への支援強化に向けて、連合会一体的・横断的事業展開として、農業経営支援事業の実施に向けた検討を進めている。そこで本研究では、今後、事業の具体化を想定している農業経営支援事業について、都府県で先行して運営されている営農サポートセンターの事業内容、体制、課題等を調査し、JAグループ北海道としての取組みに向けた提言を取りまとめることとする。
この目的に対し、今般の新型コロナウイルス感染状況を考慮しつつ調査の対象と方法を検討した。そのうえで、各関係機関へオンラインでの聞き取り調査ならびに公開資料の収集・分析を行った。調査にご対応頂いたのは、千葉県農業者総合支援センター、JA長野県営農センター、JAグループ宮崎営農サポートセンターである。これに加え、参考事例として、いしかわ農業総合支援機構、JA鹿児島中央会担い手・法人サポートセンターについて情報収集した。以上を踏まえ、連合会一体的・横断的事業展開の論点を提示した。
1点目は、「事業が先か組織が先か」をどうとらえるかという点である。調査を通して明らかになったのは、事業が下地としてあったところに、「農業所得増大・地域活性化応援プログラム」(農林中金)等を活用して、事業の受け皿としての組織をつくるという進め方と、反対に、各機関が行っていた類似の業務を一本化するという目的のもとに組織化が進められる例であった。いずれにしても、どのような筋道で組織化を進めるかを関係者間で議論し、共通の認識をもって臨むことが成否の鍵を握ると言える。
2点目は、サポートの対象者を誰に設定するのかという点である。新設する事業体(サポートセンター)に求められる役割には、「家族経営向けの総合サポート(御用聞き)」と「大規模経営・法人向けのコンサルティング」の大きく2つが想定しうる。両者のどちらを重視するかの判断が求められる。
3点目は、他機関との連携をどこまで行うかという点である。サポートセンター設置の意義の一つは、生産者にとってワンストップの統一組織ができることである。統一の範囲をどこまでに設定するのかは、生産者(受益者)の意向を踏まえながら検討していく必要がある。
4点目は、情報発信・各種手続きの一本化をどう進めていくかという点である。サポートセンターが、北海道農業のヘッドオフィスとなることの意義は大きい。「営農全般に関することはここに問い合わせればすべて解決する」組織があることは、生産者(組合員)やJAの大きな助けになる。
5点目は、各連合会の既存の業務とセンター独自の業務のバランスをどのようにとるかという点である。統一組織としてのセンターを設立・運営していくうえで、既存の業務とセンター独自の業務のバランスをどのようにとるかは、センターの存続に関わる重要な点である。
6点目は、ワンフロア化するかどうかという点である。日常的な情報交換の場にはなることは確かだが、一方で、ワンフロア化ではなく必要な時だけ集まるという方式も考えられる。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 連合会一体的・横断的事業展開に関する調査研究報告書/令和3年度北農5連委託研究事業
- 管理番号
- 704-474
- 委託者
- 北農5連
- 執筆者
- 井上 淳生、脇谷 祐子
- 発行
- 2021.12
- キーワード
- 全国、千葉県、石川県、長野県、宮崎県、鹿児島県
- 備考
- PDF公開あり(会員限定)
(4) JA・連合会と競合するサービス事業体に関する調査研究(3年目) (委託者:北農5連営農サポート協議会)
概要
JAグループ北海道が決議した「次代につながる協同組合の価値と実践」の一環で、系統組織の新たな事業展開にむけて、関連分野においてサービス事業を開始・運営している事業体について、その事業内容と運営実態を明らかにし、調査内容を報告書に取りまとめた。
報告書等
※ 未登録
(5) 農業分野における企業参入における調査研究 (委託者:北海道農業協同組合中央会)
概要
農業分野の企業参入は、国の推進する農業の成長産業化の方針の下、その数を増している。一方で、参入後の安易な撤退事例があるなど、農業生産基盤の弱体化も懸念されるところである。本研究では、農業分野での企業参入について、北海道における事例および道外で展開されている国家戦略特区の実態を調査し、その課題等を整理するとともに、JAグループ北海道の今後の対応についての提言を報告書に取りまとめた。
報告書等
※ 未登録
(6) 改正畜安法施行後における道内生乳流通の現状と課題に関する調査研究 (委託者:北海道農業協同組合中央会)
概要
改正畜産経営安定法の施行後、JAグループ北海道で生産者への公平性の一層の確保により、生乳の安定供給を図っている一方で、規制改革推進会議でのさらなる措置の必要性も論議されている。本研究では、生乳需給の安定等を通じた酪農経営安定のため、改正畜安法施行後の酪農家の生乳出荷実態を調査するとともに、卸売業者の動向や乳業者の評価等を把握し、生乳流通上の課題を整理の上、JAグループ北海道としての対応についての提言を報告書に取りまとめた。
報告書等
※ 未登録
(7) 系統経済事業における事務効率化に関する調査研究 (委託者:北海道農業協同組合中央会)
概要
現在、JAグループ北海道では持続可能なJA基盤の確立、強化に向けた取組みとして、経済事業における事務コストの削減に向けた有効な方策を検討している。本調査研究では、JAの経済事業における受発注、荷受け(入庫・仕分け)、検収、棚卸、売価設定等、なかでも生産資材購買の業務フローに関する道内外の先進事例の調査を通して、北海道のJAにおける経済事業の事務効率化の糸口を第三者機関の目から明らかにすることを目的とした。
この目的に対し、今般の新型コロナウイルス感染状況を考慮しつつ調査の対象と方法を検討した。そのうえで、各関係機関へ対面での聞き取り調査ならびに公開資料の収集・分析を行った。調査にご対応頂いたのは、JA新しのつ、JAたじま(兵庫県)である。日程調整の関係から対面調査実施には至らなかったが、JA長野中央会、JA上伊那、JA晴れの国岡山のご担当者には丁寧にご対応頂いた。
同時に、ホームセンター等の業務効率化に関する網羅的な情報収集を行った。具体的には、文献、業界誌、web上の記事を精査し、本調査に関連する項目ごとに情報を整理した。以上を踏まえ、系統経済事業における事務効率化のための、今後の論点を提示した。
1点目は、広域化したJAほど合理化システム導入のニーズが高いという点である。広域化とシステム導入の度合いの間に相関関係があることは経験的には明らかではあるが、今回、連絡をとったJAや県中央会の話を総合して、改めてこのような傾向があることが感じられた。
2点目は、上記と同様に、紙ベースでの関連業務は引き続き残るという点である。電子決裁を部分的に導入する仕組みを検討することも業務の合理化のひとつの方向性である。
3点目は、システムの内製化/外部委託は、商系にも共通する論点だという点である。特に内製化に関しては、大手企業でも検討されている点ではあるが、指揮系統の混乱が想定される課題として挙げられる。
4点目は、業務合理化を推進するキーパーソンの存在である。JAにどのようなシステムを導入するにせよ、専門的知識あるいは導入への熱意を持つ職員の存在が欠かせない。このような職員が、システムとJAを橋渡しする役割を担うからである。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 系統経済事業における事務効率化に関する調査研究報告書/令和3年度 北海道農業協同組合中央会委託事業
- 管理番号
- 716-485
- 委託者
- 北海道農業協同組合中央会
- 執筆者
- 經亀 諭、井上 淳生、脇谷 祐子
- 発行
- 2022.03
- キーワード
- 全国、北海道、関西地方、兵庫県、石狩管内、新篠津、但馬、全般
- 備考
- PDF未公開
(8) 農業分野におけるSDGs関連動向に関する調査研究 (委託者:北海道農産物協会)
概要
2015年に当時の国連全加盟国一致で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)は、2030年を期限に17の目標を掲げ、将来にわたって持続可能な経済、社会、環境を達成するための規範となっている。近年多くの産業分野においてSDGsを意識した取り組みが行われるようになり、その認知度も高まってきている。環境との関わりが大きい農業分野においてもSDGsが掲げる多くの目標と関連があり、もはやその世界的潮流から外れることは難しいともいえる。EU(Farm to Fork戦略)、米国(農業イノベーションアジェンダ)、そして日本(みどりの食料システム戦略)の農業政策にもSDGsの考えは組み込まれ、具体的に目標数値化されることで持続可能な農業の達成が目指されている。
本研究事業では、SDGs採択までの流れ、SDGsが掲げる17の目標と169のターゲットと農業の関わり、そしてSDGsが持つ多様な側面のうち、持続可能な農業の確立に向けた技術的な試みを中心に調査し取りまとめた。多くの産業分野が取り組む温室効果ガスの削減は、農業分野でも重要な課題として各種の取り組みが行われている。一つには化石エネルギーに代わる再生可能エネルギーの利用拡大が試みられており、営農型太陽光発電、バイオマス発電などが農業との関わりにおいて進められている。バイオマス発電については酪農地帯の糞尿処理とも関係し、環境的側面から重要な取り組みとなっている。農業分野での温室効果ガス排出で特徴的なのは、メタン(二酸化炭素の25倍の温室効果を示すといわれる)の排出割合が大きいことである。水田からの排出については水管理や資材利用等による対応、そして将来的に微生物を利用しようとする研究も進められている。畜産の場面では牛に与える飼料へのメタン排出低減物質の添加や微生物の利用が考えられている。農業分野では化学農薬・肥料が環境負荷を増すと考えられており、その低減が目指されている。製造側での低環境リスク農薬の開発や、利用場面での散布量低減を目指した病虫害の発生しづらい環境の整備、そしてAIなどの先端的技術を用いたスマート農業の導入などが進められている。さらに化学農薬そのものを用いない、物理的手法による病害虫防除も将来に向けて検討されている。SDGsの掲げる環境負荷低減、生物多様性維持などと関係し、農業の持続可能性を考える上で注目される有機農業について、EUと日本の農業政策においてはその面積拡大について数値目標が提示され、特に日本においては現状の数値からの大幅な拡大が目標とされた。有機農業拡大については技術的な課題解決に加え、有機農産物市場の拡大や消費者の意識改革も含めた広範な取り組みが必要とされている。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 農業分野におけるSDGs関連動向に関する調査研究報告書/令和3年度 一般社団法人北海道農産物協会 委託事業
- 管理番号
- 707-476
- 委託者
- 北海道農産物協会
- 執筆者
- 堀田 貢、及川 敏之
- 発行
- 2022.03
- キーワード
- 全国、外国、アメリカ、ヨーロッパ、全般
- 備考
- PDF公開あり(会員限定)
(9) てん菜生産における生産者の現状および意向に関する調査 (委託者:ホクレン農業協同組合連合会)
概要
てん菜は、北海道の畑作において、輪作体系を構成して地力を維持・向上させるために必要な作物であり、また、わが国の自給甘味資源としても重要な作物である。
しかし、てん菜の作付面積は昭和59年の75千haをピークに減少を続け、令和2年には57千haとなった。
てん菜の作付動向に関する研究としては、平成23年度(2011年度)に「てん菜の明日を考える会」が全道のてん菜生産者を対象に実施したアンケートの分析を行い、今後の作付振興に必要な知見を示し、平成24年度(2012年度)に、全道のてん菜生産者を対象としたアンケートと、アンケート回答者から抽出した生産者への聞き取り調査を行い、生産者の3~5年後のてん菜作付の方針別に、その特徴を整理した。
しかし、これらの調査研究から8~9年が経過し、てん菜をとりまく諸情勢は大きく変化している。そのため、本調査研究では改めて道内のてん菜生産者を対象とした生産における現状と今後の意向に関する調査を実施した。調査は、農家経営(1戸1法人を含む)および複数戸法人を対象としたアンケート調査として、令和2年にてん菜作付実績がある道内農業協同組合の協力のもと実施した。
回収したアンケートをもとに農家経営(1戸1法人を含む)および複数戸法人に関する集計・解析をおこない、現在のてん菜生産の課題を明らかにすることで、持続可能なてん菜作付に向けた対応策の検討を行った。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- てん菜生産における生産者の現状および意向に関する調査報告書/ホクレン農業協同組合連合会委託事業
- 管理番号
- 711-480
- 委託者
- ホクレン農業協同組合連合会
- 執筆者
- 西村 直樹、野津 裕
- 発行
- 2022.03
- キーワード
- 北海道、てん菜
- 備考
- PDF未公開
(10) 新たな新規参入支援体制の構築に関わる調査研究 (委託者:北海道農業公社)
概要
農業経営体の担い手として重要度を増している新規参入者については、関係機関が連携の上、その確保・拡大を進め、酪農、園芸分野を中心に着実に実績を上げてきている経過にあるが、ここ数年その勢いを欠いている。新規参入支援は、青壮年世代の夫婦を基幹とする専業的経営の創業を想定しているため、就農希望者の受け入れの時点でも「30代・夫婦」を主に想定した支援対象の限定を行っているものが多い。
しかしながら、近年の農業への新規参入をめぐる流れを見ると、従来とは異なるいくつかの特徴が現れているように思われる。それは「夫婦から単身者へ」「男性から女性へ」「30代から40歳超へ」といったように、就農希望者の属性の変化というかたちで現れていると言えよう。したがって、これからの新規参入支援は、受け入れの時点でもう少し間口を広げなければ、農業就業者の確保につながらない恐れがある。言い換えれば、従来の「画一的な受け入れ」方式には限界があり、それに代わる「多様な受け入れ」方式への転換を構想する必要がある。
さらに、この「多様な受け入れ」方式が想定する「出口」についても、見通しておく必要がある。従来の夫婦家族経営(ワンカップルファーム)に加えて、就農に強い意欲をもった単身者による営農(ワンマンファーム)、また、実際に就農事例が生まれているパートナーシップ型の経営(例えば、友人同士による創業)など、柔軟な発想が必要である。
また、今後、若年層での田園回帰の動きや、新型コロナウイルスの影響による農山漁村への定住志向など、地域への人の流動化が加速することが予想される。新たな食料・農業・農村基本計画においても、地域政策の総合化と、持続可能な農業・農村の実現を目指しているところである。
以上を受け、本研究では、新規参入者の確保・拡大の一層の促進のために、道内における最新の事例調査により、農業・農村に対する意識変化を考慮した、新たな支援方策等の仕組み構築の資とすることを目的とした。
調査先としては、道内における最新の新規参入事例の調査を実施した。最近数年間で新たな仕組みを構築してきた、知内(園芸)、松前(肉用牛)、八雲(酪農)、せたな(酪農)、富良野(園芸)、遠軽(畑作)、浜頓別(酪農)などが候補地である。
また、多様な受け入れ方に取り組んでいる事例として、道内の事例としては、①単身就農を実現した事例(計根別など)、②出資法人による単身者の受け入れを行い、将来的な就農に結びつけることを構想している事例(深川、新得など)、③多様な就農形態が生まれている都市近郊型の事例(赤井川、石狩市など)などを候補地とした。
次年度に向けて、今後は道外の事例調査も見据えながら、最終的なとりまとめに向けて調査、検討を進めていく。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 新たな新規参入支援体制の構築に関わる調査研究(中間報告書)/令和3年度 北海道道農業公社委託事業
- 管理番号
- 715-484
- 委託者
- 北海道農業公社
- 執筆者
- 東山 寛、小林 国之、正木 卓、本江 英育、廣田 佳大、端山 陽介、竹田 駆
- 発行
- 2022.03
- キーワード
- 北海道、渡島管内、檜山管内、上川管内、オホーツク管内、根室管内、知内、松前、八雲、せたな、富良野、遠軽、浜頓別、園芸、畜産、酪農、畑作
- 備考
- PDF未公開
(11) JAおとふけ中長期総合計画策定に関わるアンケート調査業務 (委託者:音更町農業協同組合)
概要
音更町農業協同組合の取り進める「第9次JAおとふけ中長期総合計画」策定に関し、生産者の意識調査に関わるアンケート調査の分析・報告書作成業務を受託した。
報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- JAおとふけ 第9期中長期総合計画に向けた組合員意向調査集計結果【経営者】
- 管理番号
- 708-477(1)
- 委託者
- 音更町農業協同組合
- 執筆者
- 野津 裕、井上 淳生
- 発行
- 2022.02
- キーワード
- 北海道、十勝管内、音更、全般
- 備考
- PDF未公開
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- JAおとふけ 第9期中長期総合計画に向けた組合員意向調査集計結果【経営者の配偶者】
- 管理番号
- 708-477(2)
- 委託者
- 音更町農業協同組合
- 執筆者
- 野津 裕、井上 淳生
- 発行
- 2022.02
- キーワード
- 北海道、十勝管内、音更、全般
- 備考
- PDF未公開
(12) せたな町農業振興ビジョンアンケート調査事業 (委託者:せたな町)
概要
せたな町の取り進める「農業振興ビジョン」策定に関し、生産者の意識調査に関わるアンケート調査の、調査票の作成および集計・分析・報告書作成業務を受託した。
アンケート結果に基づき、内容を分析の上、報告書に取りまとめた。報告書等
- カテゴリ
- 報告書
- 書誌名
- 第2期せたな町農業振興ビジョン策定のための農家意向調査結果報告書
- 管理番号
- 712-481
- 委託者
- せたな町
- 執筆者
- 正木 卓
- 発行
- 2022.03
- キーワード
- 北海道、檜山管内、せたな
- 備考
- PDF未公開